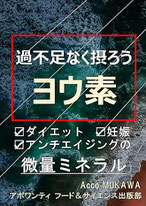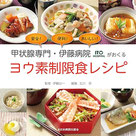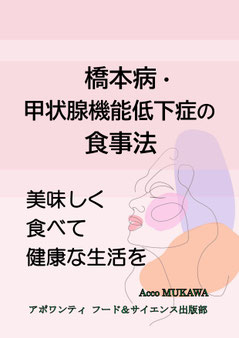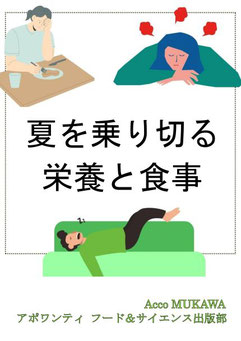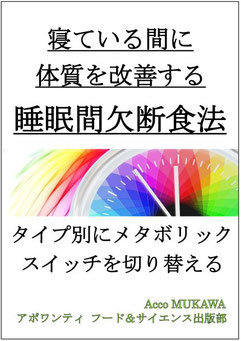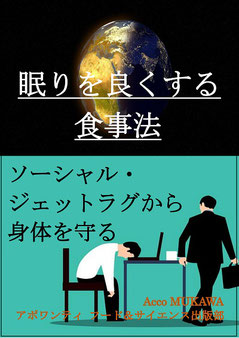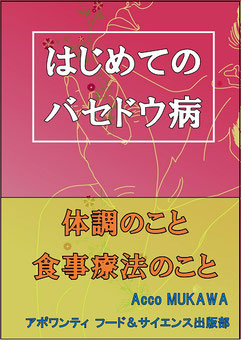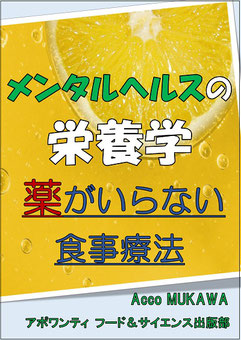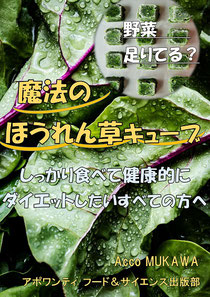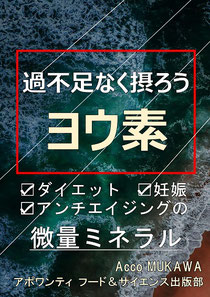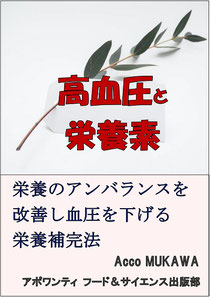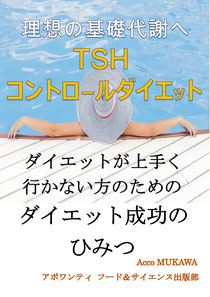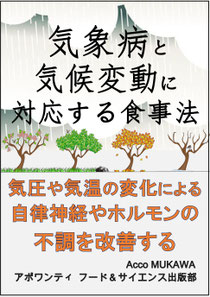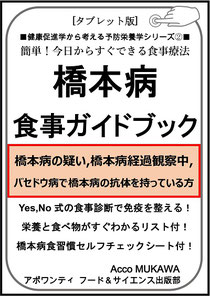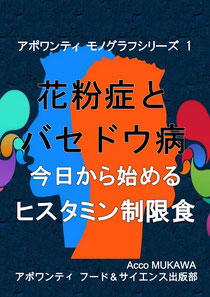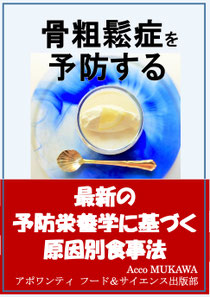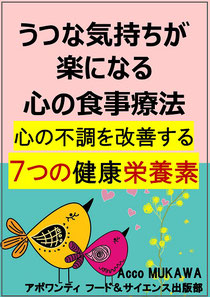橋本病の食事療法は栄養バランスとヨウ素過剰に注意
橋本病の食事療法の基本は栄養バランスとヨウ素(ヨード)の過剰や不足に注意することです。橋本病の治療中の方だけでなく、治療が不要な経過観察中の橋本病の方も食事療法が大切です。
橋本病と食事のカロリーと栄養素
食事量が増えれば太りやすくなるため、エネルギー(カロリー)の過剰摂取に注意が必要です。しかし、なかには摂取エネルギーが少なすぎることで基礎代謝が低下している方もいます。
多すぎず減らしずぎず、適切な範囲内で食事量を調整しましょう。また、カロリーだけを気にしていると、タンパク質やビタミン、ミネラル、食物繊維の不足が起こりやすくなります。 タンパク質の主菜や野菜をしっかりと食べましょう。菓子やジュースなどの栄養価の低い食品を控え、食事をしっかりととりましょう。
橋本病とヨウ素制限について
ヨウ素は甲状腺ホルモンの材料になる大切な微量ミネラルです。そのために、不足しても過剰でも甲状腺に悪影響を与えてしまいます。
ヨウ素は海藻に豊富に含まれています。「日本人は海藻をよく食べるために、ヨウ素の過剰摂取には身体が慣れている」という情報も多く見られますが、最近では過剰摂取が大きな問題になることが分かってきています。
厚生労働省の食事摂取基準ではヨウ素摂取量に対し「耐容上限量」が定められています※。
橋本病・甲状腺機能低下症で食べてはいけないものは基本的にはありませんが、ヨウ素の過剰摂取には特に注意が必要です。
海藻類の中でも昆布や昆布出汁にはヨウ素が飛び抜けて多く含まれていますので、できるだけ避けてください。それ以外の海藻類は少量でしたら問題ありません。
なお、甲状腺の検査前等に「ヨウ素制限」が必要となる場合があります。その際は、病院の指示に従って、ヨウ素制限を行ってください。それ以外では、ヨウ素は過不足のないようにしましょう。
ヨウ素が気になる方へ
ヨウ素が豊富な海藻類はどのくらい食べて良いの?甲状腺にどのような影響があるの?そんな疑問が解決するこちらがおすすめです。
橋本病とタンパク質
橋本病の方は筋力の低下が起こりやすいため、筋力を維持するために、食事中のタンパク質不足がないように注意しましょう。
タンパク質のおかずを食べる際は、必ず野菜もたっぷり添えましょう。ビタミンや抗酸化物質、水溶性食物繊維を補うことができます。
橋本病とオメガ3やオレイン酸
橋本病の方はLDLコレステロール値が高い傾向にあります。甲状腺ホルモン薬チラージンSの服用でコレステロール値は改善されやすくなりますが、食生活においても、油脂の種類に注意しましょう。 また、治療が不要な橋本病の方(経過観察中や潜在性甲状腺機能低下症の方)は、食事療法が何よりも大切になります。
オメガ3が多く含まれる青魚、亜麻仁オイル、エゴマ油と、オレイン酸やオレオカンタールが豊富なエクストラバージンオリーブオイルがおすすめです。良い油でもとりすぎれば肥満の原因になりますので、鮮度の良いものを極少量とりましょう。
肉の脂身の食べ過ぎはLDLコレステロール値を上げます。肉も質の良いタンパク源ですので、肉自体を避ける必要はありません。脂身は控えめにしましょう。
なお、消化不良を起こしやすい方は、油脂の摂取量を減らしたり、油脂の種類を変更する必要があります。
また、コレステロールというと油脂のイメージが強いですが、実際には糖質の過剰摂取もLDLコレステロール値を上げます。甘い菓子類や加糖飲料に注意しましょう。
橋本病と腸内環境・腸内フローラ
橋本病の方は腸内環境が悪化しやすいことが分かっています。腸内環境の悪化は、橋本病そのものだけでなく、便秘や肌荒れ、不眠やⅡ型糖尿病をはじめ、多くの不調や病気のリスクを高めてしまいます。体質に合った発酵食品や、水溶性食物繊維の多い野菜を食べ、腸内環境を改善しましょう。
橋本病と大豆イソフラボンについて
食品の中には「ゴイトロゲン」と言い、ヨウ素の取り込みを阻害して甲状腺腫を引き起こす物質が含まれるものがあります。食べてはいけないものではありませんが、食べ過ぎには注意が必要です。
大豆イソフラボンを多く含む食べ物、飲み物、プロテイン、サプリメントは、ゴイトロゲンに該当します。食べ過ぎることで甲状腺ホルモンの働きに悪影響を与える恐れがありますので、あらかじめ医師や管理栄養士に相談し、体質に合わないと感じたら摂取を控えましょう。
橋本病のダイエット
これまで習慣的に食べてきたものを急にやめると、かえって栄養不足が起こったり、新たな不調を感じることがあります。また、橋本病の方におすすめと言われる食品であっても、個別の体質によって合わないこともあります。食事療法を始める際は栄養バランス全体の見直しが大切です。
減量ダイエットや不調改善のための食事療法を始めたいという方のために、詳しい食事療法のご紹介や栄養カウンセリングを行っています。
橋本病の食事療法におすすめの1冊
ヨウ素制限レシピ
=電子書籍ランキング=
№1[橋本病の食事法]
№2[橋本病のための色分け栄養バランスプレート]
№3[オートミールの正しい食べ方選び方]
№4 バセドウ病食事ガイドブック
№5[バセドウ病の食事法&レシピ]
№6[橋本病・甲状腺機能低下症の食事法]
NEW!!
その他のおすすめ