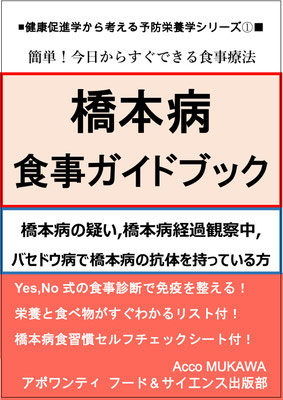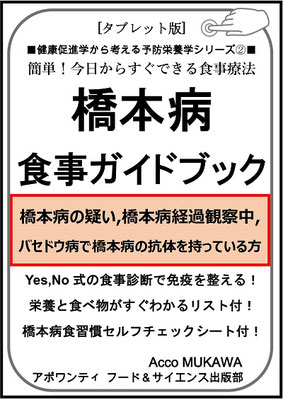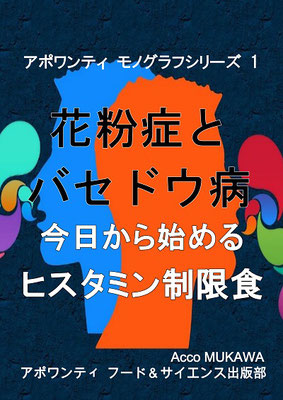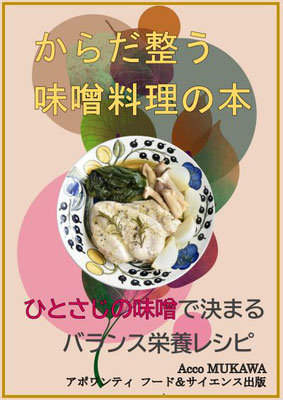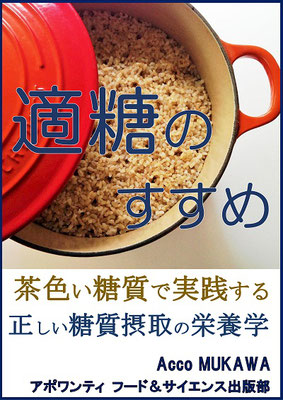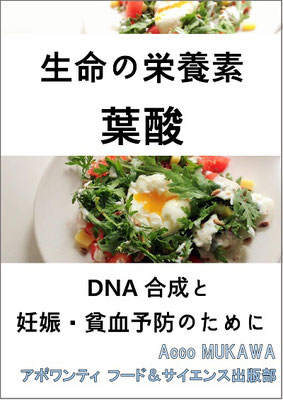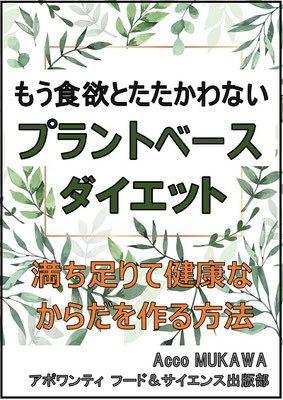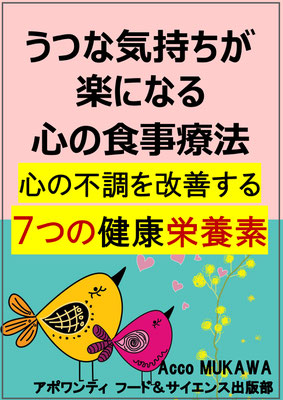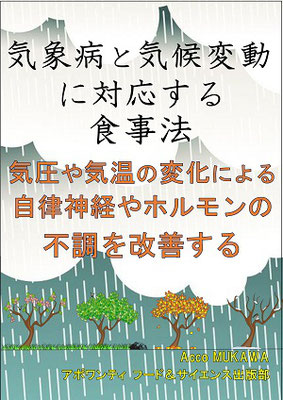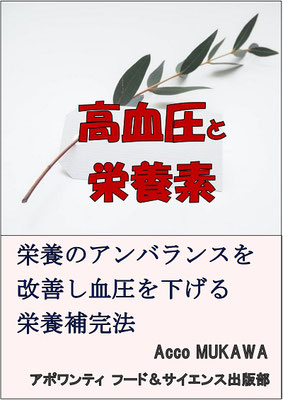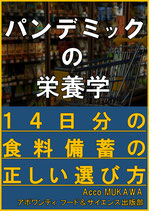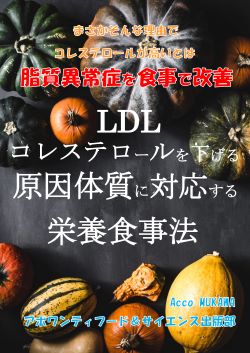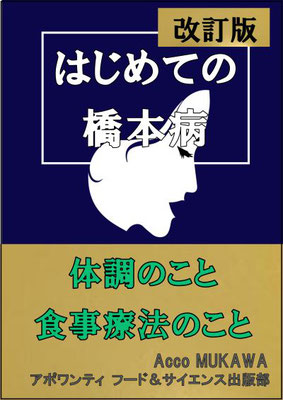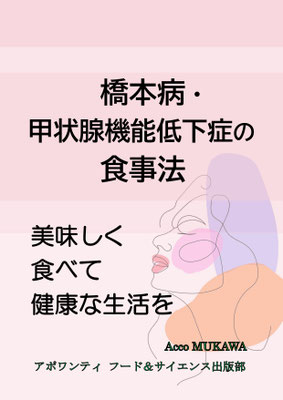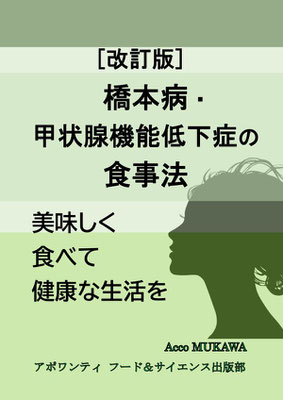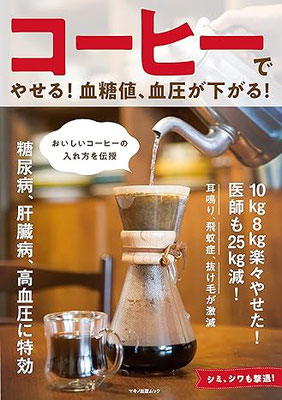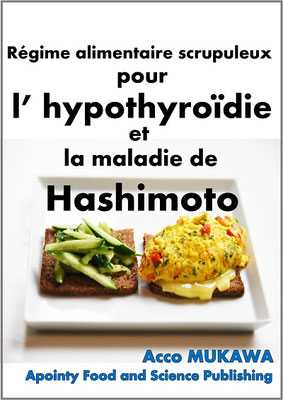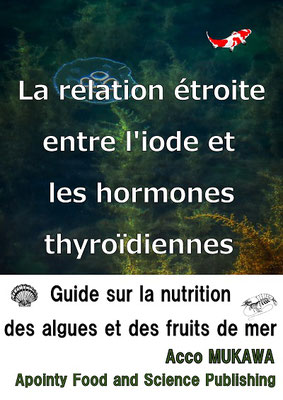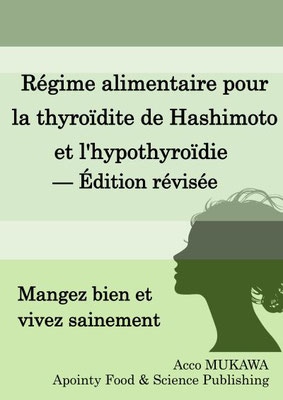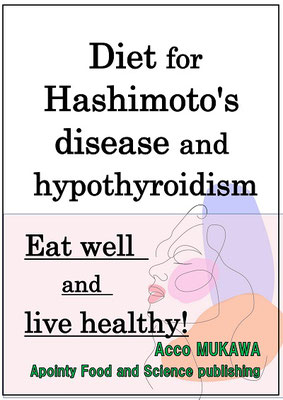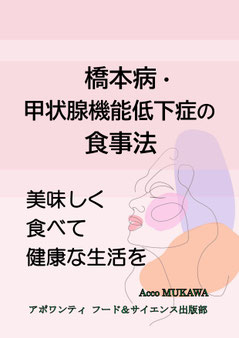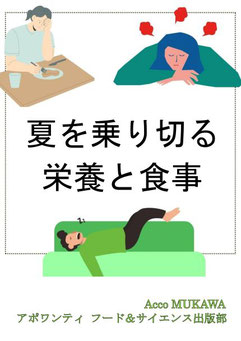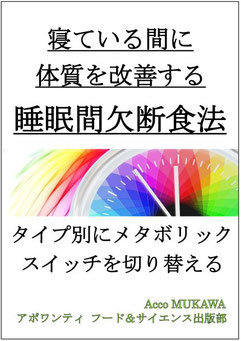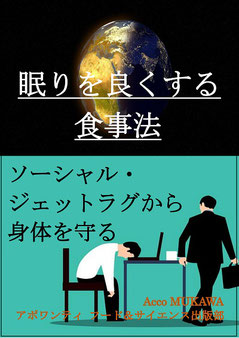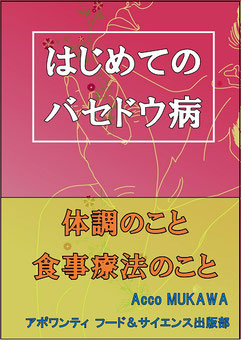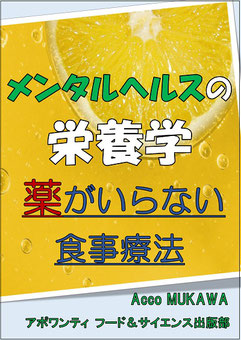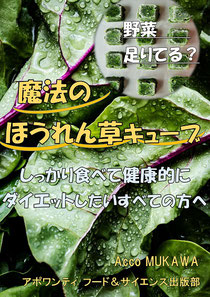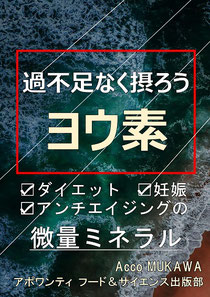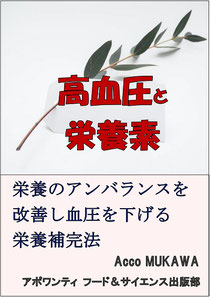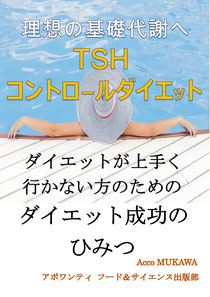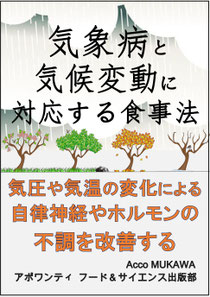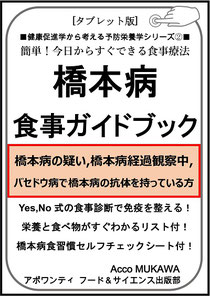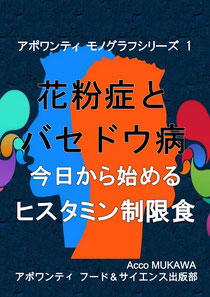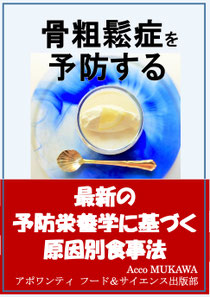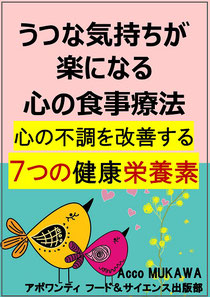橋本病とバセドウ病の食事におすすめの本一覧
はじめて橋本病やバセドウ病の診断を受けた方におすすめ
橋本病・甲状腺機能低下症の食事療法
バセドウ病の食事療法
レシピ本・体質改善に役立つ本
その他のおすすめ
ペーパーバック
多くの方々にご要望いただき、電子書籍に加えてペーパーバック(紙の書籍)の出版がはじまりました。
監修書籍
Thérapie diététique pour les maladies de la thyroïde (Version française)
=電子書籍ランキング=
№1[橋本病の食事法]
№2[橋本病のための色分け栄養バランスプレート]
№3[オートミールの正しい食べ方選び方]
№4 バセドウ病食事ガイドブック
№5[バセドウ病の食事法&レシピ]
№6[橋本病・甲状腺機能低下症の食事法]
NEW!!
その他のおすすめ





![[改訂版]橋本病・ 甲状腺機能低下症の食事法](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/s6d6d6da5b49d8e1b/image/ia25b0ab1f50b895a/version/1744416148/image.jpg)