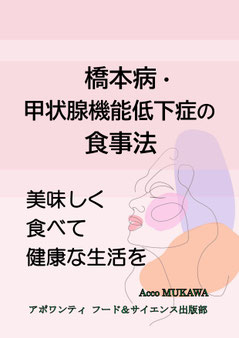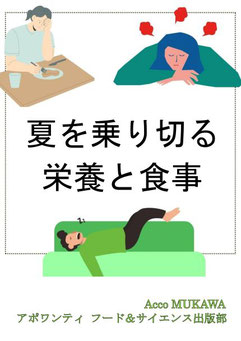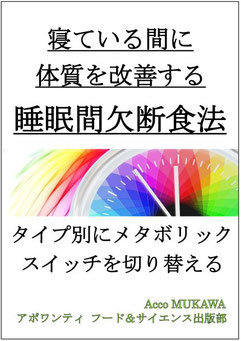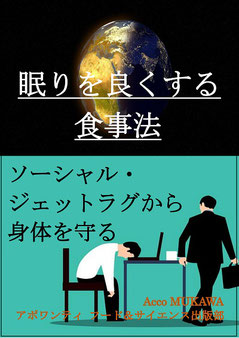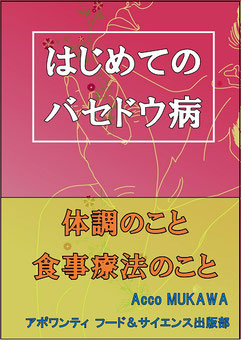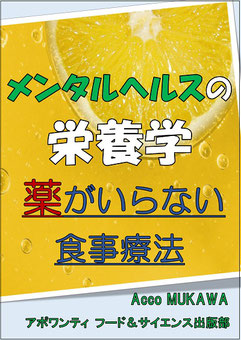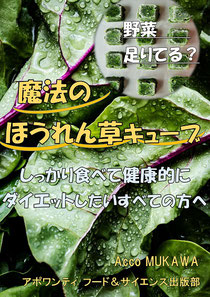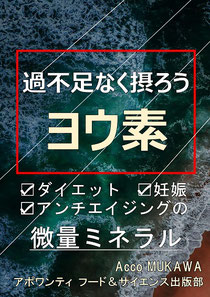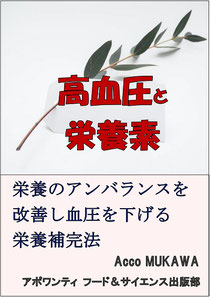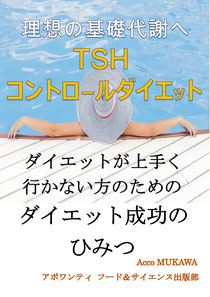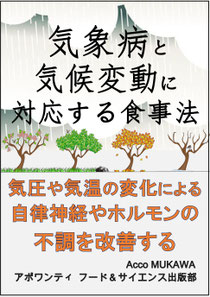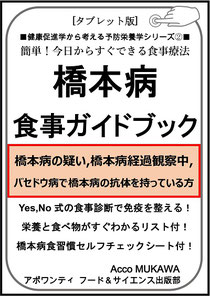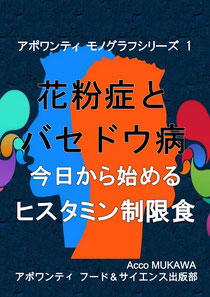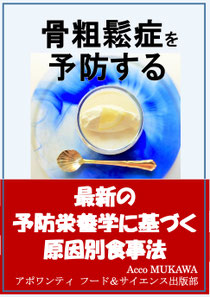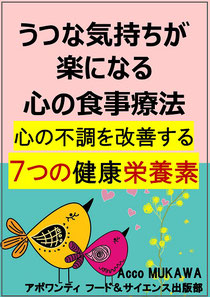だんだんと日差しの強さが気になる季節になってきました。最近話題のビタミンDは、骨の健康や免疫バランスに関わる大切な栄養素で、食事から摂取したり、日光に当たることで体内でも合成されます。前回の記事では、ビタミンDを効率よく得るために、日光浴やビタミンDを含む食品の活用についてご紹介しました。しかし、日光=紫外線には、過度に浴びすぎることで健康に悪影響を与えるリスクもあるため、注意が必要です。
過剰な紫外線がもたらすリスク
紫外線を浴びすぎると、以下のようなリスクが生じる可能性があります:
- 皮膚の炎症(いわゆる日焼け)やシミ・しわの原因
- 肌の老化(光老化)を早める
- 免疫機能の一部を抑制する働き
- 皮膚がんのリスク上昇
特に皮膚が弱い方、アトピー性皮膚炎や、SLEをはじめとする紫外線の影響を受けやすい自己免疫疾患がある方、皮膚が敏感になりやすい方は、日差しの強い季節や時間帯には十分な配慮が必要です。皮膚がんについては、日本人は白色人種に比べ、リスクが低いとされています。
紫外線に注意が必要なケース
次のような方、場面では、紫外線対策を意識することが大切です:
- SLE(全身性エリテマトーデス)など、紫外線によって症状が悪化する恐れのある自己免疫疾患をお持ちの方
- 10時~14時頃の直射日光下での長時間の外出
- 日差しが強い夏場や高地での外活動
- 肌が赤くなりやすい方や、皮膚疾患を持っている場合
- 光線過敏症(薬や病気で紫外線に過敏になる)と診断された方
- ホルモンバランスの変化でシミができやすくなっている妊娠中や更年期
- 甲状腺疾患があり、肌が乾燥しやすかったり、刺激に弱いと感じている方
- その他に光線過敏の症状が出た、出ている方
紫外線対策をしながら、ビタミンDを上手に取り入れるには?
以下のような工夫で、紫外線の害を避けながらビタミンDを確保することができます:
- 日差しの強い時間帯(午前10時~午後2時頃)を避ける
- 長時間にわたって日光を浴びることは避ける
- 帽子や日傘で顔や首を守る
- 長袖の通気性のよい服で肌を保護する
- 低刺激性の日焼け止めを使用し、肌の炎症やシミを防ぐ
ビタミンDのための日光浴は「無理をしない」が基本
ビタミンD合成に必要な日光浴は、実は1日15分程度一般的には、手のひらや腕、顔などに1日10〜15分程度日光が当たれば十分とされます(地域や季節、肌の色により異なります)。
窓越しの日差しではビタミンDは合成されにくいので、気候の良い日はベランダや日陰のある公園で短時間だけ日光にあたるのもおすすめです。
ただし、体調や肌の状態、季節によって無理をしないことが第一です。
日光浴以外からもビタミンDを
ビタミンDは食事から取り入れることができます(前回記事「甲状腺とビタミンDの関係をご覧ください)。また、必要に応じて医師や管理栄養士に相談のうえ、サプリメントを活用することも選択肢です。
まとめ
紫外線は、適度に取り入れれば私たちの体に良い働きをしますが、過剰になるとリスクもある“諸刃の剣”です。
橋本病やバセドウ病をはじめとする甲状腺疾患では、極端に紫外線を避ける対策は不要であると考えられていますが、肌が敏感な方や個別の体質や状況に応じた対策が必要です。
医師からのアドバイスや、自分の肌の状態、ライフスタイルに合わせて、無理なく、やさしく日光と付き合っていくことが、健康な毎日を支えるカギとなります。