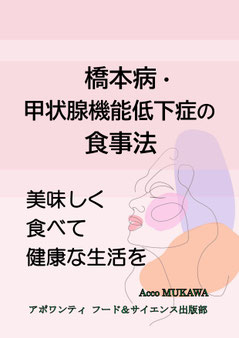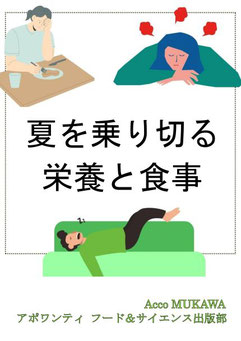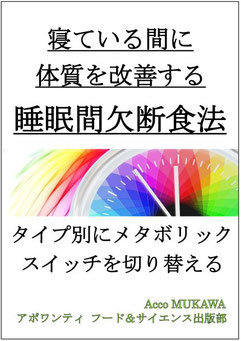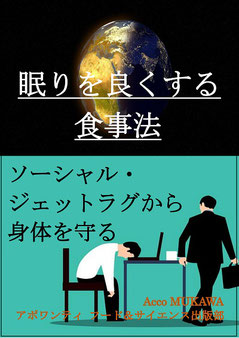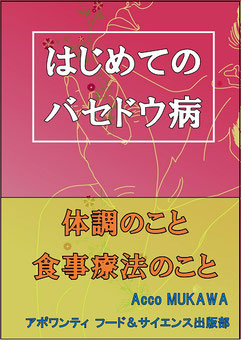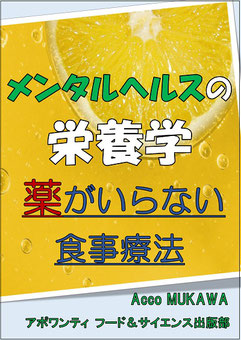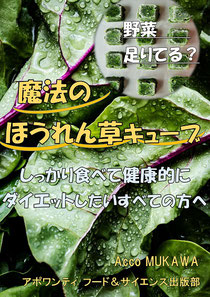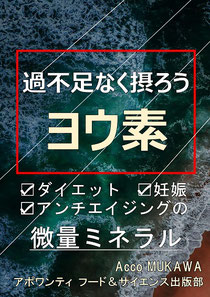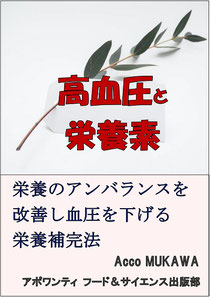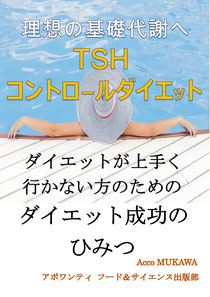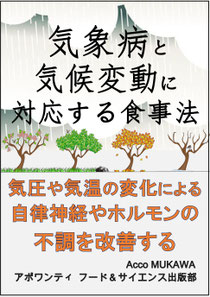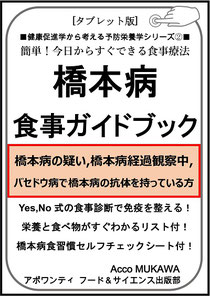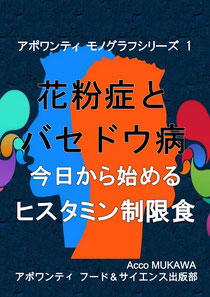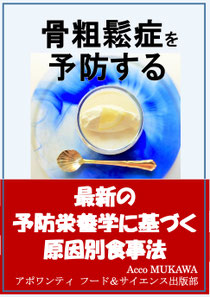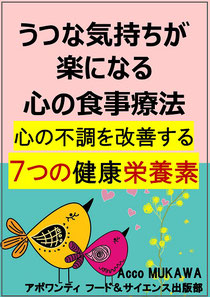ダイエットをがんばっているのに体重がまったく減らなかった、減らなくなった、という経験はありませんか? あるいは、血液検査で甲状腺ホルモン値を検査した際に「甲状腺ホルモンのT3が低い」と言われたことはありませんか? それは「低T3症候群(Low T3 Syndrome)」です。甲状腺そのものの病気ではなく、体が一時的にエネルギーを節約しようとする「代謝の省エネ状態」といえます。
甲状腺ホルモンとT3の役割
甲状腺から分泌されるホルモンには、T4(サイロキシン)とT3(トリヨードサイロニン)があります。
T4は「前駆体ホルモン」であり、甲状腺ホルモンの貯金のようなものです。これが体内で必要に応じてT3へ変換されて代謝を高める働きを持ちます。
T3は全身のエネルギー産生を促進し、体温や筋肉量、脂肪燃焼、心拍などを調整しています。
低T3症候群の原因
低T3症候群は、主に以下のような状況で起こります。
①極端なカロリー制限や糖質制限
食事量が減ると、体は「飢餓状態」と判断し、T4からT3への変換を抑えます。
これは生命を守るための自然な反応ですが、長く続くと代謝が落ち、疲れやすさや冷えを感じるようになります。
②慢性的なストレスや炎症
コルチゾール(ストレスホルモン)が増えると、T3への変換を阻害し、逆に代謝を抑える「rT3(リバースT3)」が増えることがあります。
③その他の原因
その他にも重い病気や感染、手術後などにも、体が回復にエネルギーを集中させるため、一時的にT3を減らし、代謝を抑えることがあります。
症状の特徴
低T3症候群では、典型的な甲状腺機能低下症ほど明確な症状は出ないこともありますが、次のような変化がみられることがあります。
- 疲れやすい
- 冷えやすい
- 集中力の低下
- 食事量が少ないのに体重が減らない
- 肌の乾燥や便秘
こうした状態が続くと、筋肉量の減少や脂質代謝の悪化にもつながります。
回復のための栄養と生活習慣
低T3症候群は「甲状腺の病気」ではなく、体が自ら代謝を抑えている状態です。
そのため、薬ではなく食事と生活リズムの見直しが基本になります。
炭水化物を極端に減らすとT3産生が落ちます。十分なタンパク質やエネルギーを含む食生活のなかで、糖質を適度に確保することが重要です。血糖値を急上昇させないよう、玄米や雑穀、根菜など低GIの糖質を適量とりましょう。
また、睡眠不足やストレスもT3の作用を妨げます。リラックスできる時間を意識的に作りましょう。
バセドウ病や橋本病と低T3症候群
バセドウ病や橋本病などの甲状腺疾患をお持ちの方でも、食事量の不足や無理なダイエットによって、低T3症候群のような代謝の低下が重なることがあります。
こうした状態では、だるさや冷えなどの症状が強く出るほか、十分な治療効果が得られにくくなることもあります。
甲状腺機能の異常に加えて栄養不足が重ならないよう、ご自身に合った食事量を保つことが大切です。
まとめ
低T3症候群は「甲状腺が悪い」わけではなく、体が一時的に代謝を抑えているサインです。
無理なダイエットや慢性的な疲労が続いているときほど、栄養をしっかり補い、体を安心させることが大切です。
体の声に耳を傾け、「省エネモード」から少しずつ回復していきましょう。
参考文献
Ganesan K, Anastasopoulou C, Wadud K. Euthyroid Sick Syndrome. 2022 Dec 8. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan–.