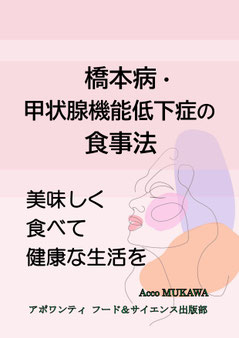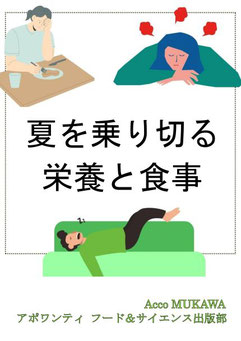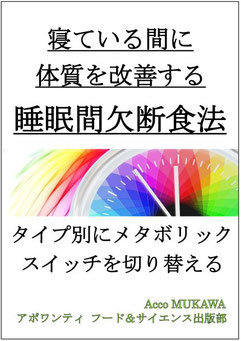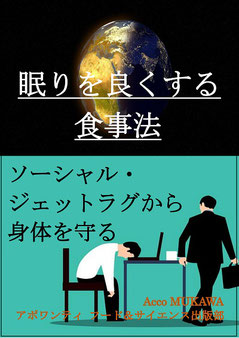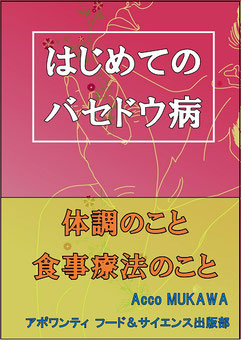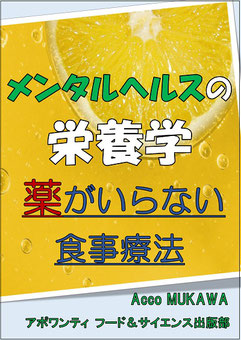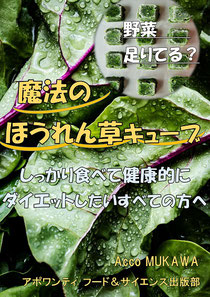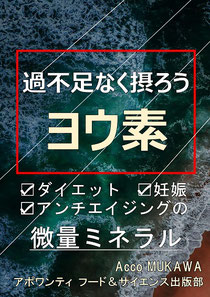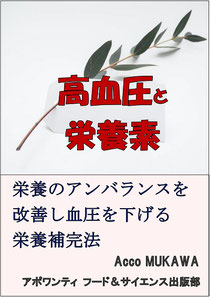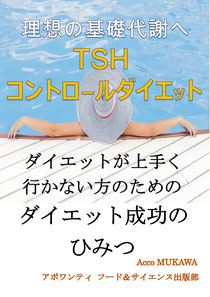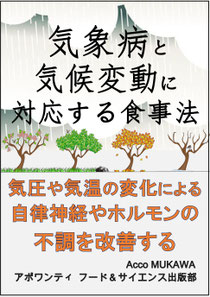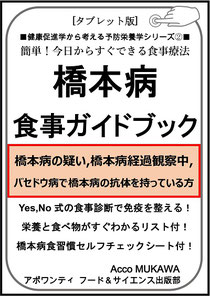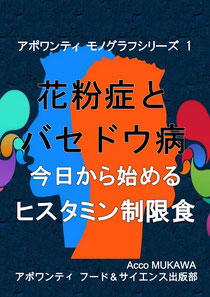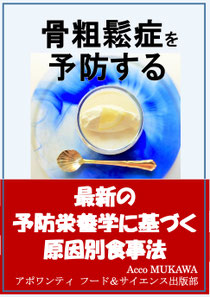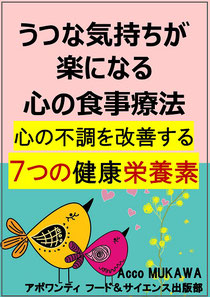バセドウ病では動悸や体重の減少等に加え、下痢や頻回の排便、吐き気や食欲不振などの消化器症状も現れることがあります。基本的な食事の工夫と注意点をわかりやすく解説します。

バセドウ病の基本症状と消化器への影響
バセドウ病は甲状腺ホルモンが過剰に分泌される病気で、動悸、体重減少、手の震え、汗が多いなどの症状がよく知られています。ところが、実は「お腹の症状」も出ることがあるのをご存じでしょうか。
甲状腺ホルモンは全身の代謝を高める働きがあります。そのため消化管の動きも活発になり、さまざまな消化器症状を引き起こすことがあります。
バセドウ病でよくみられる消化器症状一覧
- 頻回の排便・下痢:腸の動きが速くなり、便がゆるくなったり、トイレの回数が増える
- 吐き気や嘔吐:典型的ではありませんが、胃の働きが乱れることで起こる場合があります
- 腹痛やお腹の張り:腸の動きが不規則になることで、痛みや不快感を感じることがあります
- 食欲不振・早く満腹になる:食欲が落ちたり、少し食べただけでお腹がいっぱいになる
- まれに便秘:下痢とは逆に、腸の働きが乱れて便秘になることもあります
このように、多くの方は「下痢やトイレが近い」といった症状を経験しますが、吐き気や食欲低下など、幅広い消化器症状が出ることもあります。
食生活で気をつけたい基本ポイント
バセドウ病の消化器症状は、生活の工夫である程度やわらげることができます。症状のある方は、バセドウ病の治療と併行して以下のポイントに気を付けましょう。
- 脂っこい食事を控える:揚げ物や油の多い料理は消化に負担をかけ、下痢や胃もたれを悪化させやすいです
- 規則正しい食事時間を守る:食事のリズムを整えることで、腸の動きも安定しやすくなります
- よく噛んで食べる:胃腸への負担を減らし、消化を助けます
- 水分補給を忘れずに:下痢や嘔吐で失われやすい水分・電解質を意識して補うことが大切です
- 刺激物を控える:アルコール、辛いもの、カフェインなどは胃腸を刺激するため、調子が悪い時は避けましょう
症状が強い場合は無理をせず、消化の良い食事を少量ずつ摂るのも一つの方法です。
甲状腺ホルモン値と消化器症状の関係
これらの症状は「甲状腺ホルモン値が高いほど症状は強く出やすく、治療により値が正常化していくと症状も軽快する」という相関関係を示すことが多いものの、症状の程度には個人差があり、なかには潜在性甲状腺機能亢進症の段階で、こういった症状が現れることもあります。
消化器症状が続くときの受診の目安
バセドウ病というと「甲状腺の病気=動悸ややせる」といったイメージが強いですが、消化器症状も生活の質に大きく関わります。また、バセドウ病をはじめ、甲状腺疾患と診断を受けていない方で、お腹の不調が続くときは、甲状腺疾患をはじめとする、何か病気のせいかもしれません。自己判断で我慢せず、医師に相談することが大切です。
関連ページ
参考文献
Maser C, Toset A, Roman S. Gastrointestinal manifestations of endocrine disease. World J Gastroenterol. 2006 May 28;12(20):3174-9. doi: 10.3748/wjg.v12.i20.3174.
Xu GM, Hu MX, Li SY, Ran X, Zhang H, Ding XF. Thyroid disorders and gastrointestinal dysmotility: an old association. Front Physiol. 2024 May 2;15:1389113. doi: 10.3389/fphys.2024.1389113.