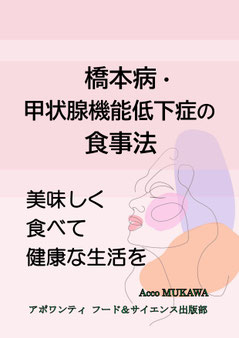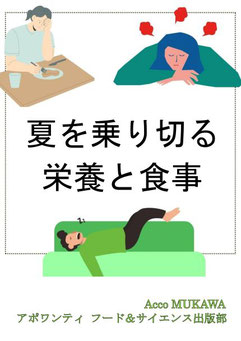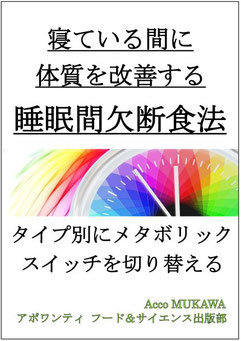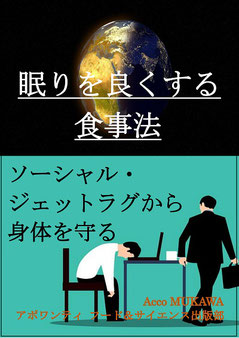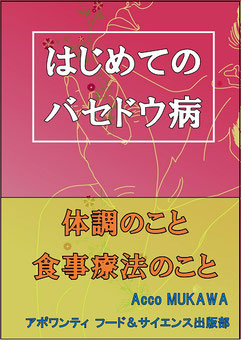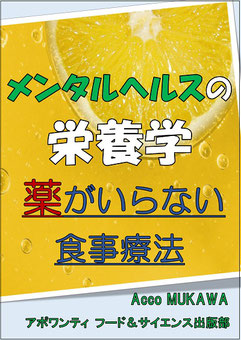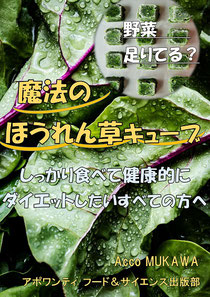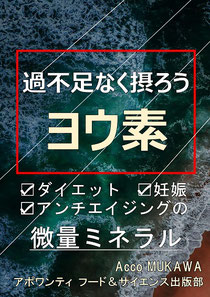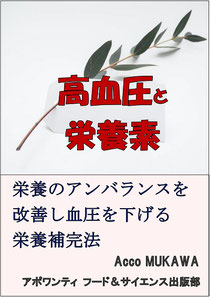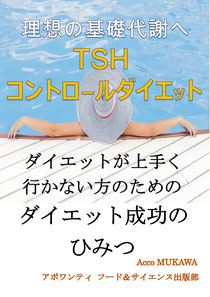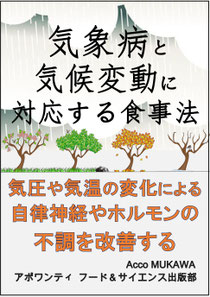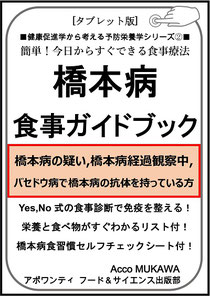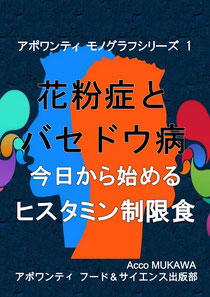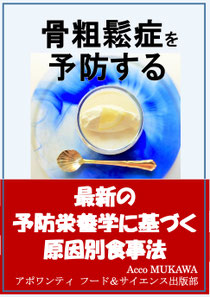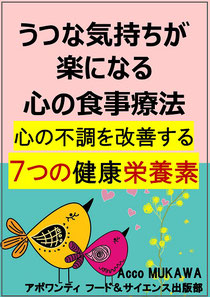甲状腺疾患には、甲状腺ホルモンの不足が生じる甲状腺機能低下症や橋本病、過剰に分泌される甲状腺機能亢進症やバセドウ病があります。これらの疾患は自律神経のバランスに影響を与え、気候の変化に対して体が適応しにくくなるため、気象病の症状を感じやすくなります。ここでは、甲状腺機能の変化と気象病の関係や対策について解説します。
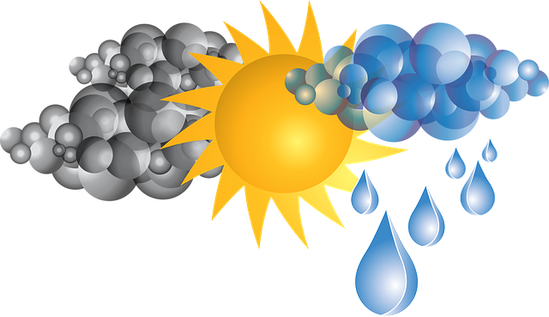
気象病(天気病)や天気痛とは?
気象病とは、天候や気候の変化により不調が生じる状態を指します。気圧や気温、湿度の変化に適応できないと、自律神経が乱れ、頭痛や倦怠感、めまいなどの症状が現れることがあります。特にストレスや疲労が蓄積していると、症状が悪化しやすくなります。
甲状腺ホルモンと自律神経の関係
甲状腺ホルモンには交感神経を活性化する働きがあります。そのため、甲状腺機能亢進症では交感神経が優位になりやすく、甲状腺機能低下症では副交感神経が優位になりがちです。
自律神経は体温調節、心拍、血圧、消化機能などをコントロールしているため、甲状腺機能の変化があると気候変動に適応しにくくなり、不調を感じやすくなります。
橋本病・甲状腺機能低下症と気象病
甲状腺機能低下症や橋本病では代謝が低下し、寒さに対する耐性が低くなります。特に気温が下がると体調を崩しやすく、以下のような症状が現れることがあります。
- 疲労感・倦怠感
- 頭痛(片頭痛)
- めまい、立ちくらみ
- 低血圧
- 冷え
- 眠気
- 消化不良(腹痛・下痢)
バセドウ病・甲状腺機能亢進症と気象病
甲状腺機能亢進症やバセドウ病では代謝が亢進し、暑さに弱くなりやすくなります。特に夏場の暑さで不調を感じることが多く、以下のような症状が起こることがあります。
- 頭痛(締め付けられるような痛み)
- 血圧の上昇
- 不安感・緊張感
- 動悸・心拍数の増加
- 発汗
- 胃痛・消化不良
- 筋肉痛、肩こり
- 不眠
気象病の対策
1. 体温調整を意識する
気温の変化が大きい日は、重ね着を活用し、体温を調節しやすい服装を心がけましょう。
2. 規則正しい生活を送る
睡眠不足やストレスは自律神経を乱し、気象病を悪化させる原因になります。規則正しい生活を意識しましょう。
3. 食生活を整える
栄養バランスの良い食事や、1日3食規則正しく食べることは、自律神経の働きに良い影響を与えます。甘いものやカフェインは一時的に不調が和らぐと感じる方もいますが、取り過ぎれば自律神経に無理な働きをさせるため、控えめにしましょう。

4. マッサージやストレッチを取り入れる
耳のマッサージや軽いストレッチを行うことで血流を改善し、自律神経の調整を助けることができます。
5. 医師に相談する
甲状腺ホルモンのコントロールが不安定な場合、症状が悪化する可能性があります。定期的な検査を受け、適切な治療を受けることが大切です。
気象病の対策まとめ
甲状腺疾患を持つ方は、自律神経のバランスが乱れやすく、気候変動に対して敏感になることがあります。特に気圧や気温の変化が激しい季節の変わり目には、体調管理を意識し、適切な対策を取り入れましょう。症状が続く場合は、医師に相談し、無理をせず過ごすことが大切です。